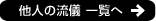JIA Bulletin 2025年秋号/覗いてみました他人の流儀
宮崎秀生 氏に聞く
空間の音響をより良くする提案を宮崎秀生

今回お話をうかがったのは、ヤマハの空間音響グループで室内空間の音響設計をされている音響コンサルタントの宮崎秀生さん。コンサートホールや劇場など、エンジニアとして建築家と協働する機会も多い宮崎さんに、音響設計の仕事についてお話しいただきました。
私は東京大学の建築学科出身で、大学院では東大生産技術研究所の橘秀樹先生の研究室で音響を学びました。入学当時はF1が全盛期でしたから車関係に進もうかなくらいに思っていました。ただ、昔からバイオリンをやっていたこともあり、ホールをつくってみたいと思うようになり、建築学科に入りました。
卒業後はヤマハに入社し、音響設計をする部署に所属しています。途中、スピーカーのシミュレーションソフトの開発に携わったこともありますが、現在は音響コンサルタントとして音響設計の仕事をしています。
ホールや劇場の設計時に、その空間の音響をより良くするために、これまでの経験やシミュレーション技術を用いて空間のつくり方をアドバイスしています。例えば、空間の大きさによって音響が変わるため、豊かな響きを得るために天井高をできるだけ確保して空間のボリュームを大きくしたり、逆に天井高を抑えて音量感を出すことを提案したりもします。プロポーザルの段階から参加することもありますが、私が関わる段階では建築家の案で空間の規模は決まっていることがほとんどです。その場合は、内装壁の拡散形状を検討したり、浮雲や音響庇と呼ばれる音響反射板を取り付けたりすることで、反射音をコントロールしながら音環境が良くなるように設計します。
香山建築研究所と一緒につくった大分県の「竹田市総合文化ホール グランツたけた」(2018年)は、700席という席数に対して空間が大きく、とても残響が豊かなホールで音楽演奏に適した音響です。一方で、残響時間が長すぎると楽器などの音がぼやけてしまうこともあるため、側壁の形状を工夫して反射音をコントロールしています。また講演会などのためには響きを抑えるために吸音カーテンも備えています。
逆に響きを豊かに変えられるのがAFC(Active Field Control)というヤマハの残響支援技術で、建築ではなく、マイクとスピーカーで自然に残響を変化させることができます。AFCを導入すると、残響時間の短いホールでも、2,000席のホールと同じくらいの残響時間にすることができます。この技術も含めて、その空間に合った音環境の設計を提案しています。
最近はイマーシブ(=没入)という言葉がよく使われていますが、音響の世界もイマーシブシステムというものが全盛期で、スピーカーメーカー各社が売り出しています。多くのスピーカーで囲うことで、音像と言われる観客が感じる音源のイメージを制御して、楽器音や声などの再生音を空間に配置したり動かしたりすることができるシステムです。
一方、AFCは1985年頃に開発されたシステムで、音場と言われる、音が響いている空間そのものをマイクとスピーカーでコントロールします。音響設計は空間から返ってくる反射音の構造を設計するのですが、いわゆる残響となる後期の反射音だけでなく、音源からの直接音の後に早い段階に届く初期反射音がとても重要で、この両者のバランスを考えながら設計を進めます。それは先ほどお話しした「グランツたけた」のように、建築的には天井高や側壁の形状、反射面の角度などでコントロールするのですが、限界があるため、それをもっと極端にできるようにしたのがAFCです。初期反射を追加したり、響きのエネルギーを追加したりすることで、ホールそのものの音場を別の音場にしてあげるような考え方です。この技術を備えている他のメーカーのシステムもありますが、音場をコントロールすることを専門としている音響設計チームが開発したシステムという点が、他と違う部分だと思っています。東京国際フォーラムのホールにも残響感や音量感を増すためにこのシステムが入っています。最近はさらに音像を制御する機能もAFCに追加されました。音響設計の技術とAFCの技術の両方のメリットを活かしながら音空間を設計しています。
空間は吸音されているブラックボックスで、響きは音響設備でコントロールするつくり方も増えてきています。また自宅で簡易にイマーシブ環境で演奏を聴くこともできます。ただ、ホールにコンサートを聴きに行く文化は無くならないと思います。やはり会場に行き、演奏者や観客の皆さんと同じ音空間を共有することの価値は大きいですし、リアルな演奏を聴くことに価値を持たせないと演奏家もいなくなってしまいます。聴く場所によって違いがあるのも面白いですから。日本はどのホールも丁寧につくられています。どんな小さな街に行っても良いホールがありますね。私はコンサートホールに行ってリアルな音を聴き、その後に飲みながら感想を話す時間が好きです。
まずは静かな空間にして、残響時間を何秒にするとこういう音環境になるという、誰にでもイメージしやすい指針があります。そこから先は設計者の感性であったり、どこまで拘るかという世界です。私はそれでいいと思っています。設計者や施主に、「響きが素晴らしいね」と言ってほしいのです。なので、何が素晴らしいのかをきちんと表現して、納得してもらうのが私の仕事だと思っています。その空間の用途やその人が何を求めているかを感じながら、言葉を選んで説明することが大切です。
私はヤマハに入社後、2002年の1年間はアメリカのある音響のコンサル会社に出向していました。当社と一緒に東京国際フォーラムの音響設計を担当した会社です。その時マンハッタンに住んでいたので、毎夜毎夜カーネギーホールやメトロポリタンなどに足を運び、オペラやコンサートを1年間で100回以上聴きに行きました。その時に、自分なりに良い音を感じたり、音を評価するスケールができたのです。これは自分にとって大きな財産です。
音響設計において初期反射のコントロールはすごく重要なのですが、それを自分なりに習得できたのはヤマハ銀座店の8階にある「ヤマハホール」(2010年)の設計です。333席のホールで、幅が狭いため横からの反射音がとても強いのです。強すぎると音像がモヤっとしてうるさいホールになってしまうのですが、そこをうまく制御することができました。実験や音響シミュレーションを何パターンも行い、こうすると音の感覚はこう変わるということを理解しながら設計できました。舞台床の木材には、ヤマハの楽器部門が持っている、木をエイジングさせる技術を用いました。エイジングされた木を使うと床の振動特性が変わり、楽器の音が変わるのです。とくにピアノやチェロなど足が床に付いている楽器は全然違います。
ホールは主階席をどう良くするかがポイントの1つですが、1,500席ほどのホールで主階席をきちんと設計できたのは「久留米シティプラザ」(2016年)です。ここではサイドバルコニー席を多層化することで良い響きをつくり出しました。それから、現在建設中の丸亀市の新市民会館のホールは、バルコニー席が壁から離して浮かんだようなつくりになっています。これはもうすぐ完成しますが面白いホールになりそうです。

自動演奏ピアノによる
舞台床モックアップを用いた試聴実験

ヤマハホール内観
社内の若いメンバーには「感性を磨け」とよく言っています。美味しいものを食べたり、美しいものを見に行ったり、いい音を聴くなど、感動するような体験をしてほしいです。それを自分でも実践するようにしています。
2003年に初めてオーストリアのザルツブルク音楽祭に行きました。とても有名な音楽祭なのですが、Tシャツにジーパンのようなラフな格好で行ってしまって…。暑い時期でもみんなタキシードやドレスで来ていて、その雰囲気に圧倒されました。それからほぼ毎年行っています。コロナ以降行っていないので再開したいです。
一緒に仕事をする建築家の方も音楽好きな方が多く、そういう方と話がしたくて普段から演奏会に足を運んでいるような部分もあります。音楽の話をするのが楽しみで、相手と感動を共有したいという思いが強いのです。楽しく仕事ができていることを嬉しく思っています。
インタビュー:2025年7月7日 建築家クラブにて
聞き手:渡辺 猛・小倉直幸・会田友朗・伊藤綾香(『Bulletin』編集WG)
宮崎秀生(みやざき ひでお)プロフィール
音響コンサルタント
1996年東京大学工学部建築学科卒、1998年同大学院修士課程修了。同年ヤマハ株式会社入社。入社後は室内音響の研究に携わり、コンサルタントとして約100件の音響設計プロジェクトやヤマハ独自の空間の音響を制御する技術である音場支援システムの設計、調整に携わる。担当した主な音響デザインプロジェクト:福岡市民ホール(2024年)、あきた芸術劇場ミルハス(2022年)、久留米シティプラザ(2016年)など。