|
2.既設駅舎へのエレベーター設置における問題点 |
既設駅舎のリニューアルにおいてエレベーター設置する場合、その既設駅舎にはどのような問題点があり、解決しなければならないのでしょうか?
(1)既設駅舎におけるエレベーター設置の問題点
新設の駅舎(駅ビル)へのエレベーター設置については、その設計段階より、スペースや動線計画を考慮したものになっていますが、既設駅舎では、元々エレベーターの設置を前提とした構造になっていないため、その設置には様々な障害があります。
■ スペース
駅舎では、大量の旅客が連続して移動するため、コンコースやプラットホームにエレベーターを設置する場所に制約を受けます。
跨線橋や地下道などは乗換機能を満たすのに必要な幅で構成され、通常幅員に余裕がありません。またプラットホーム上に工作物を設置する際に旅客の安全上、柱形状のもので最低1.0m、壁形状のもので最低1.5m、プラットホーム端部より離すことが義務付けられています。一方プラットホームは、両面使用の場合3.0m以上、片面使用の場合2.0m以上(端部では、両面使用の場合2.0m以上、片面使用の場合1.5m以上)の幅とするとの規定があります。当然これは最低を定めたものであり、乗降客数により必要な割増は考慮されていますが、さらにエレベーター設置の場合、その分の幅員が必要となり、十分な幅員が確保出来ないところが多いのが現状です。
■ ピット寸法
プラットホームには構造上の制約があり、プラットホーム下を線路面より深く掘削することは、線路防護上必要な措置をとる必要が生じ、多大な費用を要することとなります。また、構造によっては、掘削そのものが不可能な場合もあります。このため、少なくともピットの高さを線路面からプラットホーム上面までの高さ(1.1m程度)以下に抑えることが望ましく、ピットの浅い(ピットレスの)エレベーターが要求されます。(図2−1a)
■ オーバーヘッド寸法
また、プラットホーム上部は鉄骨造の屋根で覆われているものが多いですが、プラットホームから屋根までの高さは3〜4m程度であり、このためエレベーター昇降路の上部にオーバーヘッドスペースを確保することが困難となり、必然的にオーバーヘッド寸法の少ないエレベーターが要求されます。屋根に開口を設け、昇降路を突出させることも考えられますが、多大な工期と費用が発生すると共に、雨漏り等の問題が発生することが予測され、非常に難しいと思われます。(図2−1b)
|
|
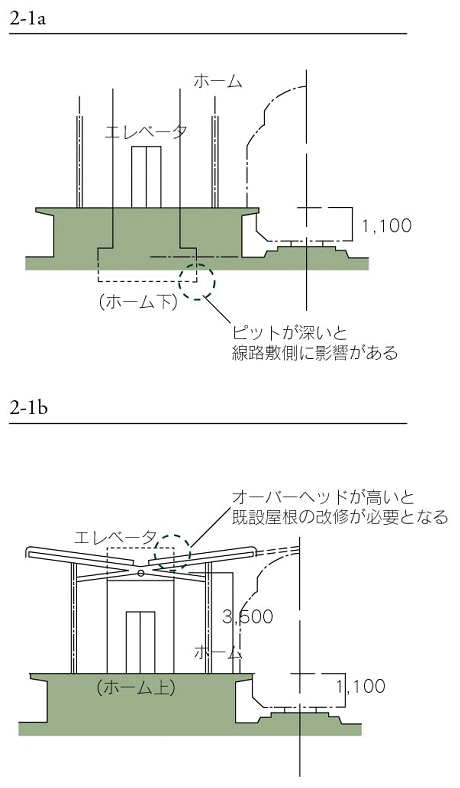 |
■ 前後及び直角ニ方向出入口
プラットホームには、通常排水のために、その幅方向の中心から両側の線路方向に向けて、勾配を設けてあり、このため、プラットホーム上でエレベーターの出入口が線路と直行方向にある場合は、特に車いすがかごを出入りする際には、線路に向かって非常に狭いスペースの勾配を上がり下がりすることとなり、防護柵等の落下防止措置がとられていない場合には大変危険です。従って線路と平行に出入口を設けることが望ましく、これはプラットホーム上での旅客の流動方向とも一致し、その流れを妨げることもありません。一方、跨線橋、コンコース等の通路においては、旅客の流動方向は多くの場合線路と直行方向となり、例えば通路中央部に設ける場合のエレベーターの出入口は、プラットホーム同様に、この方向に向いて用いられることが望ましい。この場合は、エレベーターの出入口は上下で90度異なることとなり、直角二方向出入口のエレベーターが要求されます。また、通路の片側に設ける場合のエレベーターの出入口は線路と平行方向となり、この場合は上下で出入口は0度または180度の方向となります。そのため、前後出入口のエレベーターが要求されることになります。(図2−2) |
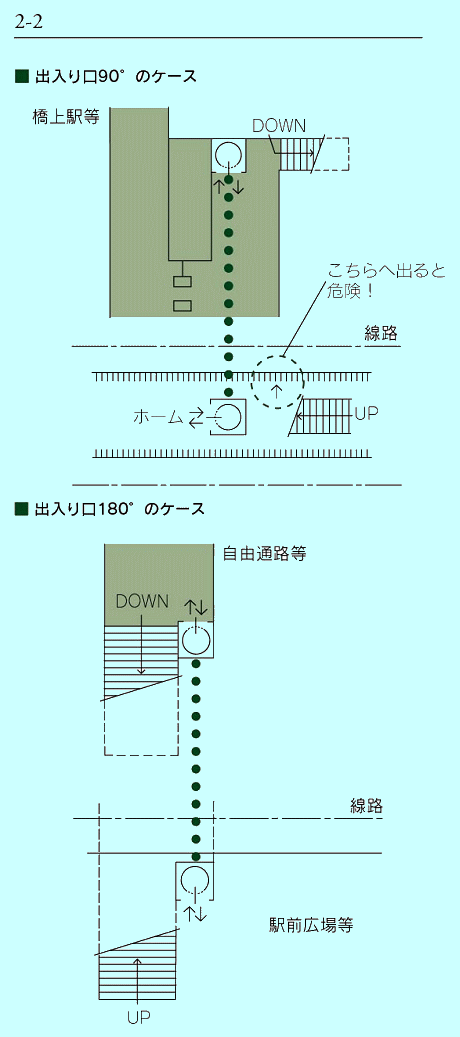 |
(2)駅舎リニューアルにおけるエレベーター昇降路の構造
既設駅舎のリニューアル工事における重要ポイントは、通常、旅客が列車への乗降及び駅施設の利用を行なわれている中での工事になると言うことです。そのため、安全に注意することはもちろん、出来るだけ工期を短縮することが要求されます。よって、新設でよく採用される鉄筋コンクリート構造の昇降路は採用されず、そのほとんどが鉄骨造による昇降路構造となります。
また、夜間駅舎が利用されていないわずかな時間(3〜4時間程度)で工事を行なわなければならない場合もあり、その場合は工事区分を明確にし、その範囲で一気に工事を完了しなければならず、よって昇降路についてもユニット式等、簡易に組み上げて行くような構造とされたものが要求されると思われます。逆にプラットホームまでの工事動線が複雑で、クレーン車等の乗入れが困難な場合では、その昇降路を分割式にして、部材として搬入後、現地にて組立てなければなりません。
昇降路構造については、その他、自立式と半自立式に分類され、高架式や橋上式等、プラットホーム等の床構造がしっかりおり、昇降路の周囲をサポートできる場合には半自立式を採用出来ますが、地上式の跨線橋等、軽微な構造のため、昇降路の荷重を依存できない場合では、自立式の採用が要求され、コストアップとなります。(昇降路構造に関する詳細については、『E-box Spring'97』参照)
|
   |