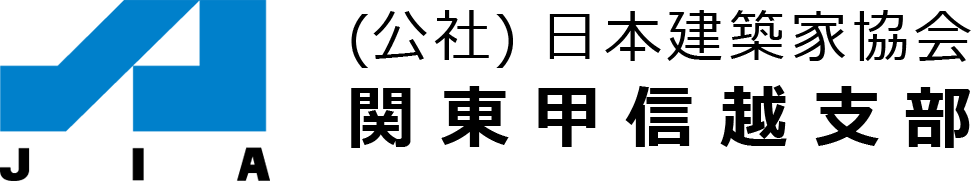|
■ これまでの歩み
子供のころの思い出や原風景のようなものがあったらお聞かせください。
生まれ育った当時の高田(上越市)には新潟大学の芸能科(音楽・美術・書道・体育)というものがあって、そこで行われる展覧会や定期演奏会などに小さい頃から連れられて行っていたようです。また、父親が文化的な活動もしていて、市役所の講堂に時々夜、母親に映画を見に連れられて行った記憶があるのですが、あとで思い出せばあれはユトリロだったんだなとか、赤い風車は記憶にあるからこれはロートレックだな、とか今で言うとおそらく岩波映画のようなものを父親が友達と上映会をやっていたようです。地域で文化的な活動をしていると非日常的なことが持ち込まれてくることもそうだし、そのような会をつくるというのはそれなりの苦労があるはずで、そのような活動をしていた父の影響や、それを温かく見守る母親との家庭がとてもいい雰囲気だったように思っていて、それは僕の原点の一つかも知れないと後に思いました。
美術との出会いやこの仕事を始めたきっかけをお聞かせください。
高校3年生くらいから、この先どうやって生きていこうか考えていました。高校卒業後に上京し、アルバイトしながら東京にいるのですが、そんな中、京橋にあった当時の近代美術館で京都市立芸術大学の村上華岳の修了制作の絵をみたことと、上野の西洋美術館でボナール展を見たのをきっかけに、絵を描きたいと思い美術の道に進むことを決めました。
芸大の芸術学科に入学後、しばらくは絵を描いていたんですが、学生運動の波がついに芸大まで押し寄せて、絶対にかかわらないと決めていたんですが結局かかわることになってしまいました。ただそのときに、古美術研究会という授業で仏像を見るチャンスがあってそれに驚いて、その後も先生にもいい形で教えを受け、今の素養になっています。僕のベースは仏像彫刻あるいは文人画・南画といわれるもので、これは一生懸命に勉強しましたし、すごくいいものを見せてもらいました。僕はどちらかというと研究者向きではなかったので、その後の道を模索していましたが、銀座などの画廊に毎日夕方いろいろな絵を見て廻るなどの勉強をする中で、結局美術も隣の芝生だということに気づいて、つまり美術の問題ではなく、日本のコミュニティーや明治以降の社会に問題があると気づき、絵描きになることをやめて、裏方にかかわることを決意しました。最初は、仲間や友人たちとグループで、デパートの内装工事やインテリアの仕事などをやっていました。
あと、仏像で学んだのは、例えばここに仏像があるとして「仏像がつくる空間」というのがあって、「つくる」というのは属するの「属」です。普通は「空間に仏像が属している」という表現をします。部分と全体の関係で言うと全体が大きくてそこにあるものは空間に属している、ある意味では伽藍、お寺の本堂の中に属していると言います。この「属」には違う言い方があって、「仏像が属(つく)る空間」という言い方をするのです。空間に属していながら廻りに変化を与える、という言葉によく現れていて、両方で押し合っている関係性を表しているんです。そういう意識があって、博物館に持ってきても仏像ではあるけれども仏像がつくる空間は何もない、あるいは空間によってつくられる関係もない。これは僕にとって決定的な素養だと思います。ですから美術館からアートが出て行くことは僕にとっては必然だったんです。
もうひとつ、「美術」に関して言うと、「美」は、人間の手、アーティフィシャルなもの、人がかかわったという意味で、「術」はその方法です。彫刻や絵画はその一つですが、アルタミラ、ラスコー以来、美術とは自然、文明、社会と人間の関係を表す技術・方法だったわけです。
例えば数学で、「ここから富士山まで100kmありますよ、だからこのように見えますよ」というのもひとつの科学的なアプローチの方法ですが、一方、北斎が逆さ富士を描いたりするのは直感的に捉えた富士山、これも一つの富士山を表しているものであって、どちらがいい悪いではない。直感的な富士山のほうが面白いし的確な場合もある。そういうものとして僕は美術を捉えているので、社会的に問題がある場所で美術が効かなければ美術って意味がないと考えて活動しています。
もう一つ違う言い方をすれば、物事が平均化、角質化する社会の中で、セグルメントしてものを決めようとする。例えば、AからZまで70億人いるとして、足してアルファベットの数で割ると「M」「N」が真ん中で、これが人間なんですよという捉え方をする。これが平均的な人間像です。一方、美術の面白さは70億人全員違うこと。だから、圧倒的に多様なほうがいいとか、必ずしも近道がいいとは限らないと考えていて、それが僕の流儀といえば流儀です。だから、越後妻有はとても手間暇がかかっていて、合併の施策にのった事業でありながら760平方キロの中のほとんど200集落全部に関わってやっています。

イリヤ&エミリア・カバコフ 《棚田》
「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」
撮影:中村脩
|
■ 大地の芸術祭について
著書※1に、芸術祭を認知させていくきっかけとして「反対者と同じ立場にたつ」というお話がありましたが。
地域づくりではこれまで美談が多いんです。理解者とやるのは確かにいいとは思いますが、現代美術とまちづくりのひとつのきっかけとしてやる場合、それでは変わらないだろうと思っていて、行政と物事を進めると皆税金払っていますから今までの積年の恨みを行政に言いますね。しかも現代美術はあまりよく思われていないので反対者が出てくる。その反対者と一緒にやらなければ物事が進むわけないです。僕らがどれだけ真剣なのかが試されていて、4年半で2000回を越える会議をやってましたから、それじゃやらせてみようという雰囲気になっていって、やってみたら少しずつ面白くなってきたという感じです。要するに美術は手間暇かかるし面倒くさいし、メンテナンスはかかるしなんだかわからない、だけど何か気になるもの。赤ん坊みたいなものなんです。美術には、赤ちゃんのように周囲をなごやかにして、人と人をつなげる力があると思いました。
媒介者としての「こへび隊」※2のことや、都市の人間が地域を求めているとはどういうことですか。
大地の芸術祭では恐らく何十万人も来ている。それは新潟の里山が面白いぞとか、アートがなかなかいいぞというのは勿論ありますが、都市の人間が田舎を欲していなければこれほど移動するわけはない。つまり、都市には刺激や興奮、大量の消費もあるけど本当に住んでいくときに皆がいいと思っているかといえば微妙ですね。僕らも心の中では「うっ」と思いながら生きているわけです。
地域では一人一人が一人の人間として受け入れられますが、都市の中では自分は置き換え可能です。グローバリゼーションの中では、受験勉強をやり就活して入った会社がある日突然吸収合併されたりしているわけで、一人一人の大切さという部分に関しては極めて厳しいですね。彼らは自分が自分としてかかわれる、受け入れられる場所を探しているはずで、それがなければこへび隊は成立していません。地域の人の属性を言うと、中山間地で農業をやっているお年寄りです。最初の数回のこへび隊は、都市部の学生、若者、外国人ですね。つまり、地域・世代・ジャンルが180度違う人間がかかわることで起きる化学変化によって動き出したという感じです。こへび隊の媒介者としての意味は極めて大きかったと思います。実際、十日町とか、高齢者はまだ働いているんですが、支えていく力があまりない。若い人が来てかかわってくれることが彼らにとってはすごく嬉しいんですね。

カサグランデ&リンターラ建築事務所 《ポチョムキン》
「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」
撮影:安斎重男
|
■ 瀬戸内国際芸術祭について
特に印象に残っていることをお聞かせください。
当然のことなんですが、島がこんなに一つ一つ違うのかということが驚きだったですし、船に乗るということがこんなに日常生活から違う気分になるということが面白かったです。お客さんもそうだったと思います。これは私たちの先祖からの遺伝子が騒ぐんだと思いますね。

五十嵐靖晃 《そらあみ》「瀬戸内国際芸術祭」
撮影:高橋公人
|

リン・シュンロン(林舜龍) 《国境を越えて・海》「瀬戸内国際芸術祭」
撮影:高橋公人
|

安部良《島キッチン》 「瀬戸内国際芸術祭」撮影:中村脩
|
■ 中房総国際芸術祭 いちはらアート×ミックスについて
経緯と芸術祭を通しての印象的な出来事についてお聞かせください。
市原については、手一杯でできないとお断りしていたんですが、市長と市の職員がとても熱心で一度市原に行ったんです。首都近郊だからあまりやりたくないと思っていたんですが、南市原は市原市全体の半分くらいのエリアにもかかわらず、人口は十分の一以下でコミュニティーは崩壊寸前。これは普遍的な姿だと思ってかかわらせていただきました。統合された廃校、小湊鉄道という単線にこだわって、そこから何か考えたいと思って始めました。市原湖畔美術館は既存の建物のリニューアルで、今後リノベーションは多くなるはずだから今後のためにとプロポーザルコンペをやるところからはじめました。ただ、収蔵作品があるわけではないので地域の文化芸術活動の拠点として位置づけてやっています。美術館だから面白い展覧会はやるんですが、市原のキャッチフレーズは「晴れたら、市原行こう。」。美術館のミッションには「ピクニック」もあるのです。
それで、この間やったのは、「おにぎりのための、毎週運動会」で、お昼時に小学校の校庭で運動会をやるんですよ。来た人が紅白に分かれて、8回開催したんですが、途中からもう満員。80歳以上のおばあちゃんもゼッケンをつけて、皆でお昼にはおにぎりを食べるというイベントでとても好評でした。
つまり、過疎になっていくのはある意味必然ですが、学校は地域の思い出の場所。合併しても学校がなくなるとよりどころなくなるのでそれはなんとかしたいと思っていたし、日本の運動会は学区の運動会で小学生だけのものではないんですね。おばあちゃんや幼稚園児も加わってやれるような運動会は日本にしかないんです。人がいなくなれば運動会もできないし、お祭りもできない。これを、よその人達を受け入れてやれるしくみをつくらないと地域がだめになると僕は思っているので。地域と都市の「交換・交感」がいろんな形でできるというのが重要だと思っています。
あと、「指輪ホテル」の芝居が評判で、これは小湊鉄道の車内で芝居をやるんですが、車窓の田園風景も取り込むのです。トンネルの中を真っ暗にするとか、駅じゃないところで降りるのを国土交通省とたいへんなやりとりをして特別に許可をとってやりました。最後のクライマックスはそこで生きてた地霊(ゾンビ)と車掌さんが仲良くなって、一緒に菜の花のところに楽隊を連れながら行くんですが、感動で涙が出てくるんです。
また、市原では「食」をアートに取り込んでやっていますが、食べ物は地域を一番表していますね。地域のファンになるのは、食べ物を通してなります。とても重要なことだと思います。建築家も割と食べ物にこだわりますよね。食に関心をもち、いいものを食べないといい建築も設計できないと思います。特にパブリックな建築をやる建築家は。

KOSUGE1-16 "湖の飛行機”
「中房総国際芸術祭 いちはらアート×ミックス」
撮影:中村脩
|

EAT & ART TARO ”おにぎりのための運動会”
「中房総国際芸術祭 いちはらアート×ミックス」
撮影:中村脩
|
■ 今後の抱負
今後の展望、展開についてお聞かせください。
越後妻有については今までのいろいろな反省があって、今後はもっと深く入ろうと思っています。
いよいよ地域のそれぞれの集落と独自のきっかけをもてる何かを少しずつやりたいなと思っています。都市と地域の交換も必要ですが、地域内の交換もやり始めないと持続しないですね。やり方も少しずつ変えるなど考えています。それと、次回はパフォーマンス系が多く入る予定です。
■ 建築家への期待
最後に建築家へ期待することについてお聞かせください。
それはもう、建築家がいろんな場所で手伝ってくれています。建物をつくろうとするときにクライアントの方向に対して一番アドバイスできるのは建築家です。そこはすごく重要な役割だと思っています。妻有の場合は、廃校・廃屋を中心にやっていますが、市原のリニューアルもそうですが、今後もそのテーマは大きくなると思います。
あと、建物をつくることだけではなくて、地域の問題や地域住民の様々な要望に対し、アドバイスや提案をするようなコミュニティーの建築家がたくさんでてきてほしいですし、僕らも建築家にはその部分からお願いしてやっているので、やはりいいものができあがります。
一方で、新しくつくるものについては、建築家が全部つくるのではなく「余白」が求められている時代なのではないでしょうか。
クライアントにとっては一生に一度新築できたら大事業ですし、その後に商売の形態も変わる可能性もあるわけで、フレキシビリティや余白を含めた部分は必要になってくるんでしょうね。建築家が世の中のいろんな場面でキーになっていると思います。そういう意味で言うと、良し悪しは別にして、昔、ある建築家が美術館のある公共の文化施設をやるときに、「美術館は学芸員の頭脳がすべてだ」と言ったのもそうだし、また別の建築家が美術館をやるときに、「建築家がやれることは美術館のソフトの予算を首長にたくさん取りなさいということだ」と立派なことを言いました。首長さんは建物を建てたがりますがそのあとをあまり考えてませんから、収蔵品は別にして、ソフトの予算だってないことだってたくさんあるのです。そういうことを最初に建築家が一言言えば大きく変わりますし、そういう役割が建築家にはあると思います。建築家は、建築家であると共に哲学者でもあってほしいと思っていますね。猛烈に。
■インタビューを終えて
梅雨の晴れ間のある日の昼下がり、代官山のオフィスを訪ね、お話を伺いました。取材冒頭、「気楽に始めましょう」と、私たち取材側にお気遣いいただき、その後、和やかな雰囲気の中、ゆっくりと言葉を選びながらお話をされる姿が印象的でした。
北川さんはご自身の役割を「裏方」という言葉で表現されていますが、アートを広義に捉える姿勢そのものに既に表も裏もなく、アートを媒体にして人や地域を元気に豊かにしていきたいというご自身のテーマは、今後の建築家の役割とも重なる部分もあり、多くの刺激を受けました。
〈聞き手:八田雅章・植木健一〉
※1 『美術は地域をひらく 大地の芸術祭10の思想』(現代企画室刊)
※2 大地の芸術祭を支えるサポート組織
■北川 フラム(きたがわ ふらむ)氏プロフィール
アートディレクター
1946年新潟県高田市(現上越市)生まれ。東京芸術大学卒業。
主なプロデュースとして、「アントニオ・ガウディ展」(1978-1979)、日本全国80校で開催された「子どものための版画展」(1980-1982)、全国194ヶ所38万人を動員し、アパルトヘイトに反対する動きを草の根的に展開した「アパルトヘイト否!国際美術展」(1988-1990)等。
地域づくりの実践として、2000年にスタートした「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(第7回オーライ!ニッポン大賞グランプリ〔内閣総理大臣賞〕他受賞)、「水都大阪」(2009)、「瀬戸内国際芸術祭2010、2013」(海洋立国推進功労者表彰受賞)等。
|
|
 |
長年の文化活動により、2003年フランス共和国政府より芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。2006年度芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門)、2007年度国際交流奨励賞・文化芸術交流賞受賞。2010年香川県文化功労賞受賞。
2012年オーストラリア名誉勲章・オフィサー受章。
「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」、「瀬戸内国際芸術祭」、「中房総国際芸術祭 いちはらアート×ミックス」の総合ディレクター。
◇現職および公職
公益財団法人福武館財団常任理事、(株)アートフロントギャラリー代表取締役会長、青山学院大学・香川大学・神戸芸術工科大学他客員教授、岡山大学学長特別補佐、(財)地域創造顧問等
URL http://www.artfront.co.jp
|
|